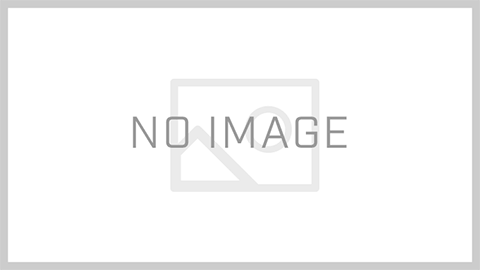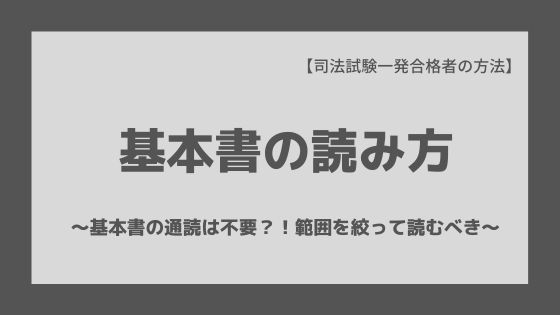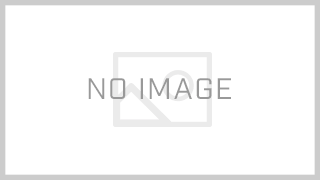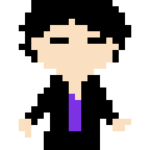(この記事はプロモーションを含みます。)
こんにちは
今回は六法について説明していきたいと思います。
私は法律の勉強をしているのですが、よく友人や知人から、「六法って何?」という質問を受けます。
確かに、法律の勉強をしていない人からすれば、法律のイメージとしては六法全書があるけど、そもそも「六法」って何なのかわからないですよね。
私も最初は何で六法というのか疑問でした。
昔は、六法全書はあんなに分厚いのに、法律ってそんなに少ないのかぁ、とか思っていたものです(笑)
そこで、なぜ六法と呼ぶのかということや各法律の特徴について簡単にまとめておこうかなと思います。
これから法律系の仕事と思ってに就きたいと思っている人や、法律の勉強をしたいと思っている人はこの記事を読めば「六法」とは何なのか、ということが簡単にわかると思いますので、是非読んでください。
Contents
六法とは
さて、皆さん六法全書は聞いたことがあると思いますし、みたこともあるのではないでしょうか。
弁護士のドラマとかでよく出て来ますね。
リーガルハイとかみてた人はきっとイメージできるのではないでしょうか。
黒くて分厚いあれですね。
その六法全書が何かと言うと、簡単に言えば、法律の辞典みたいなものです。
六法全書の中にはいろんな法律が載っているのですが、決して6個の法律だけが載っているわけではありません。
そもそも、六個だけであんなに分厚いわけもありませんし、日本の法律は約2000ほどあります。
では、なぜ「六法」全書なのでしょうか。
それは、日本には基本となる法が6つあるため、それらをまとめて「六法」と呼んでいるのです。
簡単に紹介すると、六法は
1.憲法
2.民法
3.刑法
4.民事訴訟法
5.刑事訴訟法
6.商法(会社法)
の6つになります。
実は、これら6つの法をまとめて「六法」と呼んでいるだけなのです。
日本にはこれらの他にも、例えば、道路交通法や地方自治法など、数多くの法律が存在します。
しかし、それら多くの法律の基本法が「六法」なのです。
それぞれの法律の特徴
1.憲法
憲法は日本における最高法規です。
つまり、日本の法規でピラミッドを形成すると、頂点に君臨するのが憲法ということになります
その内容は大きく分けて、人権分野と統治機構分野の2つとなります。
人権分野としては、例えば表現の自由(憲法21条)や生存権(憲法25条)があります。
統治機構分野は、司法、国会、内閣に分かれます。それぞれの機構の構成や各種手続き等を規定しています。
ちなみに、憲法は最高法規性があるため、憲法に違反するような法律は無効となります。
最近は憲法改正の議論が盛り上がっていますので、認知度も高くなっていますね。
2.民法
民法は私人間の法律関係を規律する法律です。
つまり、AさんがBさんに金を返せとか、CさんがDさんと離婚したいとなった時に出てくる法律が民法ということです。
現在、条文の数が1044という多さです。
ちなみに2020年頃に改正民法が施行されることが決定しています。
3.刑法
刑法は犯罪行為と刑罰を規定しています。
例えば、殺人罪(刑法199条)や窃盗罪(刑法235条)があります。
ちなみに、最近改正されて、性犯罪が厳罰化されました。
参照記事:刑法改正について解説 性犯罪が厳罰化!!
4.民事訴訟法
私人間の法律関係で争いがあった時に裁判で解決することになりますが、その際に使うのが民事訴訟法です。
つまり、民事系の事件に関する裁判について規定したものということになります。
例えば、民事訴訟を起こしたい時にどのような手続きが必要か、どこの裁判所に訴える必要があるのかといったことについての規定があります。
5.刑事訴訟法
犯罪行為をした者を処罰する裁判の手続きについて規定している法律です。
例えば、警察による犯罪捜査方法や、刑事事件の裁判の進行、裁判で使われる証拠等についての規定があります。
大きく分けると、上記のような、捜査・公判・証拠、という3つの分野に区別できます。
6.商法(会社法)
商取引のルール等を規定した法律です。
商法(会社法)となっているのは、会社法が商法からスピンオフして新しくできたものであるからです。
なので、現在は、商法と会社法は別の法律ですがもともと同じ法律だったということで、まとめて扱われることが多いのです。
会社法については、その名の通り、会社の組織構造や権利義務関係、会社に関する手続き等について規定しています。
もしも、起業したり株主になるなら会社法のお世話になるかもしれません。
最近は六法じゃなくて七法?!
さて、上記の通り、基本的な法律が6つあるから「六法」と呼ばれるのですが、最近では一つ増えて「七法」と言われることもしばしばあります。
上記の法律に加えて、「行政法」も合わせるべきだという人が多くなったのです。
このように、行政法が加わった理由は、行政関係の法律が増えてきてそれに伴い行政事件も増加したことから重要性についての認識が高まったからだと思われます。
司法試験や司法試験予備試験等の各種法律試験でも、六法とともに行政法も出題されることとなったことも、行政法の重要度の高まりを表していると言えます。
ちなみに、「行政法」という名前の法律は存在しません。
あくまで、行政分野の法律の総称を行政法と呼んでいるのです。
また、従来のように「六法」という呼称に慣れている方の一部からは、憲法は最高法規で法律と同格ではないため、行政法を入れたとしても憲法を除いて「六法」と呼ぶことにしようという流れもあります。
「六法」であれ「七法」であれ、上記に出てきた基本法は全て大事なので、もしも法律を学習しようと考えているのであれば、ここに出てきた法律知識はきっちりと身につける必要があります。
最後に
以上、今回の記事では「六法」とは何かということについて書いていきました。
少しはイメージがつかめたのではないでしょうか。
もしも、法律について興味が出てきた人は、まずはこの記事に出てきた法律を基本に勉強していくことになると思います。
この記事が少しでも皆さんのお役に立てる者であれば幸いです。
それではまた