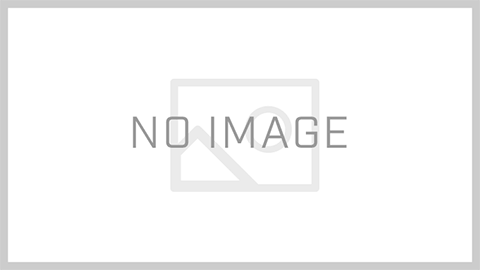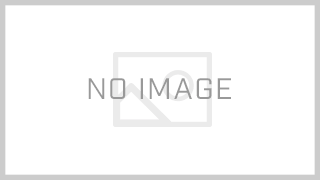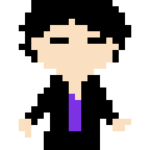(この記事はプロモーションを含みます。)
【重要度】★★★★☆
刑事訴訟法の重要論点の一つとして、おとり捜査の合法性があります。
おとり捜査の合法性については二分説という学説と判例の整理が非常に大事になります。
なので、今回はおとり捜査の論点について判例や学説をまとめておきたいと思います。
今回書く内容だけ理解できていれば、基礎的な部分については十分でしょう。
必要最小限度の説明でなるべくわかりやすくまとめます。
刑事訴訟法が苦手な人や初学者でおとり捜査に興味を持った人には是非読んでいただきたいです。
また、最後におとり捜査が論文問題で出てきた時にどう書くべきか、論証パターンを示しておきたいと思います。
是非最後まで読んでください。
ー参考文献ー
古江頼隆『事例演習刑事訴訟法 第2版』(2015)147-158頁
川出敏裕『判例講座刑事訴訟法〔捜査・証拠篇〕(2016)196-207頁
 |
事例演習刑事訴訟法 第2版 (法学教室ライブラリィ)
古江 頼隆 有斐閣 2015-03-11
|
 |
判例講座 刑事訴訟法〔捜査・証拠篇〕
川出敏裕 立花書房 2016-03-14
|
Contents
おとり捜査とは?
判例によると、おとり捜査の定義は
おとり捜査は,捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が,その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け,相手方が これに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するもの
です。
つまり、警察等が被疑者が犯罪をするように働きかけて、犯罪行為を行ったらその人を逮捕するという捜査手法です。
このような手法に対しては、警察等の捜査機関は本来犯罪を取り締まるべき存在なのに、その捜査機関によって犯罪が作られることになるから、おとり捜査は認められるべきではない、という批判があると思います。
確かに、おとり捜査はわざわざ犯罪行為をさせてから、実際にやった場合には逮捕するという、かなり卑怯な方法であるとも思われますよね。
しかし、学説や判例はこのようなおとり捜査も認められる場合があっていいと考えています。
注意していただきたいのは、おとり捜査が絶対的に許容されるということでも、どんな場合でも認められないということでもないということです。
あくまで、おとり捜査が合法であるか違法であるかの判断基準について議論がなされているのです。
機会提供型と犯意誘発型
それでは、上記のような批判を踏まえた上で、学説上はおとり捜査の合法性をどのように考えているのでしょうか。
学説上、二分説という考え方があります。
二分説は、下記のようにおとり捜査を⑴機会提供型と⑵犯意誘発型に分けて考えます。
⑴機会提供型:すでに犯罪を起こす気がある者に対して、その犯罪行為の機会を提供するにとどまるもの
⑵犯意誘発型:犯罪行為を起こす気がないものに、積極的に働きかけて、犯罪行為をする気を起こさせるもの
そして、学説上のおとり捜査の合法性の判断は、⑴機会提供型は合法であるのに対して、⑵犯意誘発型は違法であるとします。
つまり、すでに犯意がある者ならその機会を提供したに過ぎないのだから、捜査機関が犯罪を作り出すという批判は当たらない、一方で、犯意がない者にそのやる気を起こさせるのは上記の批判がそのまま当てはまり許されるべきではない、と考えるのです。
このように、おとり捜査を⑴機会提供型と⑵犯意誘発型の二つに区別した上で、それぞれ合法、違法になるというように、形式的に合法性を判断するのが二分説という学説です。
おとり捜査の判例
では、上記のような二分説に対して、判例はどう考えているのでしょうか。
以下に判例を引用します。
参考記事:【刑事訴訟法】おとり捜査の重要判例・裁判例まとめ
【最決平16.7.12刑集58.5.333】百選10
(判旨)
2 以上の事実関係によれば,本件において,いわゆるおとり捜査の手法が採られたことが明らかである。おとり捜査は,捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が,その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け,相手方が これに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するものであるが、
【要旨1】少なくとも,直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,通常 の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に,機会があれば犯罪を行う 意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは,刑訴法197条1項に 基づく任意捜査として許容されるものと解すべきである。
【要旨2】これを本件についてみると,上記のとおり,麻薬取締官において,捜 査協力者からの情報によっても,被告人の住居や大麻樹脂の隠匿場所等を把握することができず,他の捜査手法によって証拠を収集し,被告人を検挙することが困難な状況にあり,一方,被告人は既に大麻樹脂の有償譲渡を企図して買手を求めてい たのであるから,麻薬取締官が,取引の場所を準備し,被告人に対し大麻樹脂2kg を買い受ける意向を示し,被告人が取引の場に大麻樹脂を持参するよう仕向けたと しても,おとり捜査として適法というべきである。したがって,本件の捜査を通じ て収集された大麻樹脂を始めとする各証拠の証拠能力を肯定した原判断は,正当と して是認できる。
判例はこのように、おとり捜査は機会提供型なら合法で犯意誘発型なら違法であるという形式的な判断をしていないことがわかります。
しかし、判旨の中で「機会があれば犯罪を行う 意思があると疑われる者を対象に」と言っている以上、機会提供型であるか犯意誘発型であるかという点が合法違法の判断の一要素になっていることがわかります。
つまり、判例はおとり捜査は機会提供型なら合法で犯意誘発型なら違法であるという形式的な判断をせずに、諸般の事情を総合的に考慮した上で合法違法を判断しているといえ、その判断の要素の一つに機会提供型か犯意誘発型かという点が含まれていると考えているのです。
おとり捜査の論証
というわけで、おとり捜査の合法性について論文試験で問われた場合、上記のような判例の考え方に従って論証するべきです。
具体的には、おとり捜査も普通の捜査の合法性判断基準と同様に、その方法の相当性を総合考慮によって判断するということになります。
以下で論述の流れを軽く示しておきたいと思います。
これを参考に適宜必要な部分があればそれを補充していただけたらと思います。
【論証例】
おとり捜査が合法であるか。
まず、おとり捜査が強制処分に当たるかという点が問題となる。
なぜなら、おとり捜査を許容した条文はなく、従って強制処分に該当するなら強制処分法定主義に抵触する恐れがあるからである。
しかし、おとり捜査は強制処分には当たらないと解する。
そもそも、強制処分とは重要な権利利益に対する実質的な侵害を伴う行為を指すところ、おとり捜査には重要な権利に対する制約は伴わない。
そのため、強制処分には該当しないものの、おとり捜査には捜査機関による犯罪創出という面があり、無制限に認められるものと解することはできない。
従って、おとり捜査が合法か否かは、当該具体的事案の事情に応じて、おとり捜査をする必要性や捜査方法の相当性を総合的に考慮した上で判断するべきである。
⇨当てはめ(囮捜査の対象となる犯罪の種類や機会提供型かどうかという点を考慮しながら当てはめる)
このような流れで書けばとりあえずは大丈夫なのではないでしょうか。
あくはで論証の流れを示したものなので、必要に応じて加筆修正していただけたらと思います。
少なくとも、おとり捜査についても強制処分と任意処分の区別という点や任意処分としての合法性判断を使いながら、その枠の中で論証をしていけば十分だと思われます。
あとは、当てはめで様々な事情を拾い上げて、機会提供型なのか犯意誘発型なのかという点も触れた上で、しっかりと書くことができればいいと思います。
まとめ
今日は、刑事訴訟法の重要論点の中でも、学説と判例の関係で理解が難しい、おとり捜査の合法性について書いていきました。
学説の二分説に対して判例が総合考慮による相当性の判断という方法を採用しているという点が非常に重要です。
今回引用した判例を読んで、どのような事実を取り上げているのかという点も確認していただきたいです。
何か質問があればコメントください。
ちなみにオススメの刑事訴訟法の参考書を以下にあげておきます。
 |
刑事訴訟法入門 第2版 (法セミLAW CLASSシリーズ)
緑 大輔 日本評論社 2017-09-19
|
最後まで読んでいただきありがとうございます、
みなさんの学習に少しでも役に立てたなら幸いです。
それではまた